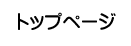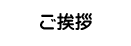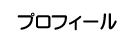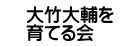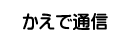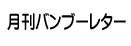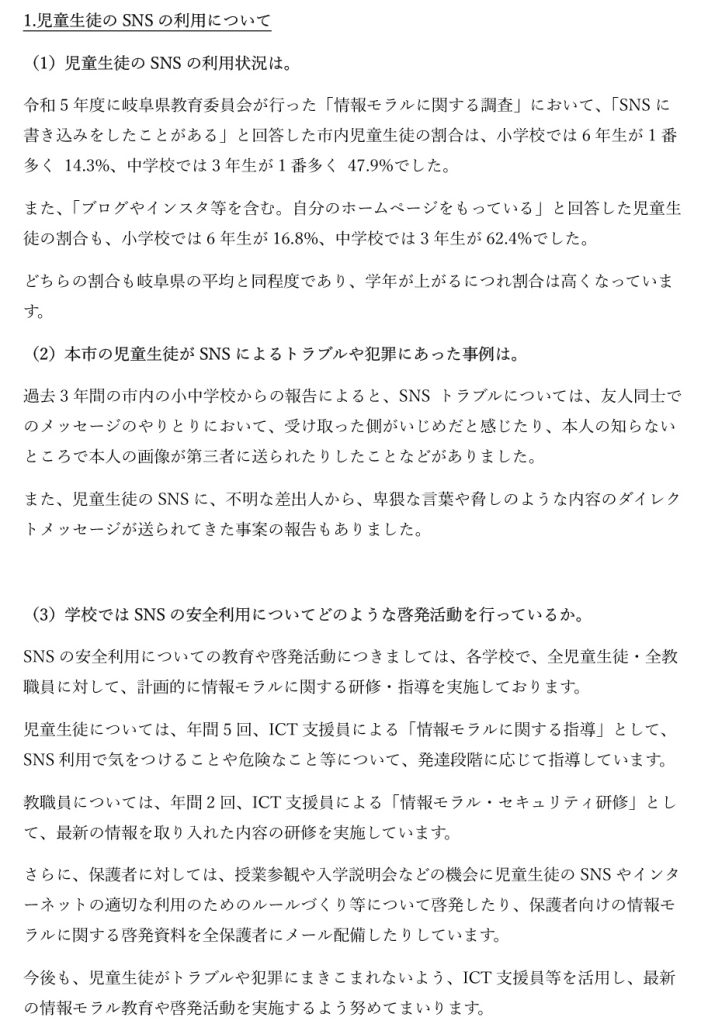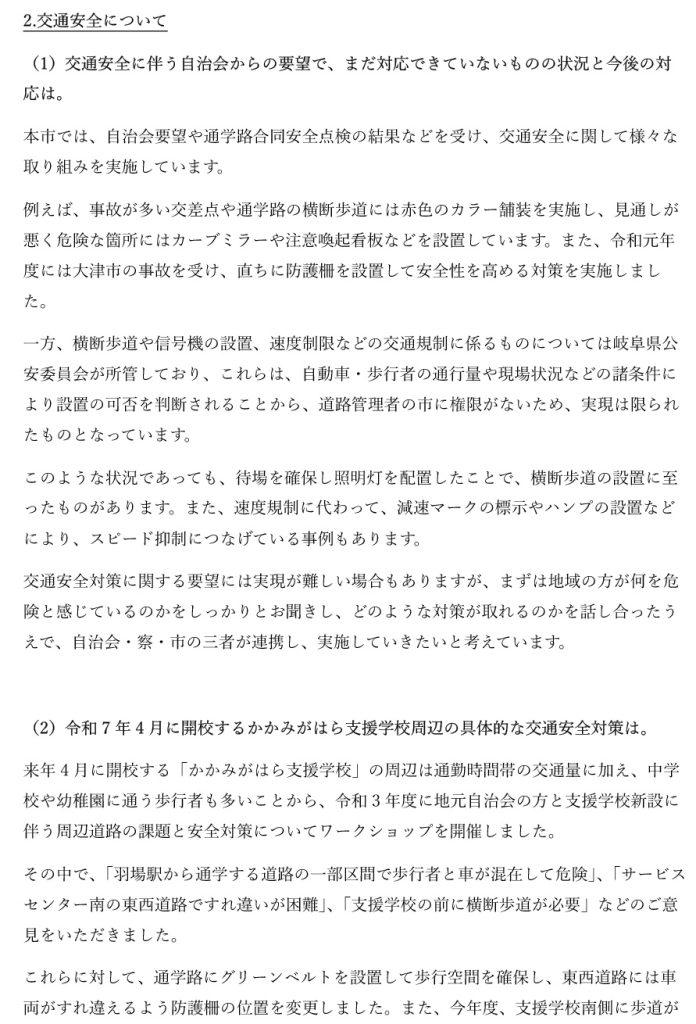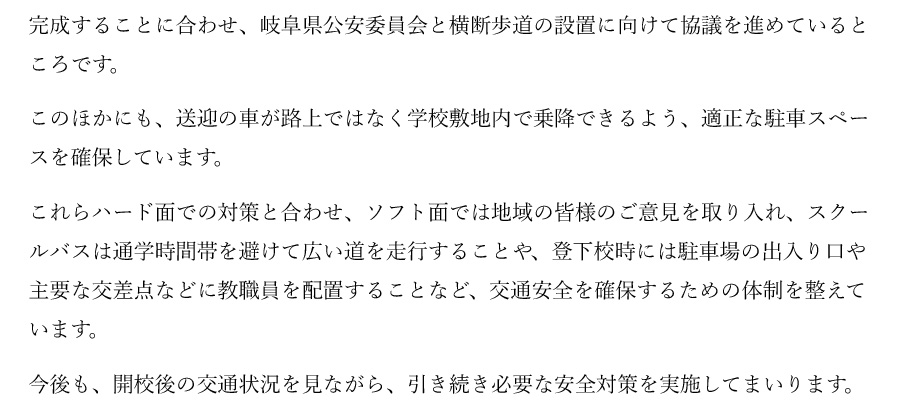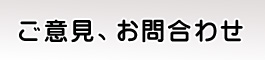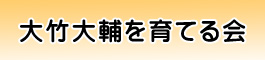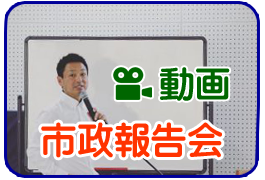令和6年各務原市議会第5回各務原市議会定例会一般質問
颯清会 大竹大輔です。議長に発言お許しいただきましたので、通告に基づき質問させていただきます。
今回は、大きく2点質問しますので、よろしくお願いいたします。
それでは、一つ目質問、本市の児童生徒のSNSの利用ついて質問致します。
2019年に提唱された文部科学省の取り組みであるギカスクール構想により、教育現場でICT機器が積極的に活用されるようになりました。
本市でも、全ての児童生徒にタブレット端末が貸与されており、ICT機器がより身近なものなったと思います。
私の子どもが小学校に通っておりますので、小学校の授業参観に行くことがありますが、ギガスクール構想の取り組みが始まって5年経ち、先生も児童生徒も、タブレット端末や電子黒板などの機器を当たり前ように使っており、ICTを活用した教育(授業)が浸透していることが伺えます。
とくに子どもたちは、全てではありませんが、ゲーム機器などでこれらのICT機器の活用に慣れているので、大人以上に吞み込みが早く、私自身もタブレット端末の使い方を小学生の子どもたちに聞くこともあります。
さて、このように教育の現場でICT機器が活用されておりますが、こども家庭庁の青少年のインターネット利用環境実態調査を見ると青少年の約98%がインターネット利用しており、既に子どもたちの生活の中には、自宅にこれら(パソコン、スマートフォン、タブレットなど)の機器があるなど、教育現場以外でもタブレットなど使う機会が多くあり、小学生の高学年や中学生など年齢が高くなるにつれて、スマートフォンやタブレット端末を自分で所有する率も高くなり、(友達同士のコミュニケーションツールとして、ゲームの端末として、また、塾や習い事の送迎で親との連絡手段などで使っている状況です。
これらスマートフォンなどは、ゲーム機のように、ただ遊ぶ手段(ツール)ではなく、日々の生活の中で、連絡手段、行先のナビゲーション、調べ物をするなど、当たり前のように使われており、大人同様、子どもたちの生活の中にも浸透というより密着したものになっております。
このような状況下、これらを使うことに伴う様々なトラブルや犯罪が発生しております。
子ども家庭庁のホームページの中にあるで、警察庁のインターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止についてという資料を見ますと、SNSに起因するの被害児童数の推移は、平成25年からのデータを見ますと増加しております。(ここ最近は、令和元年から横ばい状態ですが、とはいっても高い値で推移 1732 4.4%減)
特にSNSは、容易にインターネット上で交流したり情報共有でることもあり、便利な故にSNSに伴うトラブルや犯罪に巻き込まれる事案が発生しており、年々増加傾向にあります。
また、SNSの活用が多様化していることも、トラブルや犯罪の増加に繋がっていると考えます。
特に昨今では、SNS経由により容易に違法薬物を入手でき、若年層にこれら広まっている現状は、食い止めなければなりません。
スマートフォンは、便利であり、また各々が個別で持つ端末であるため、親などや第三者の目が行き届かないこともあり、我が子がトラブルや犯罪に巻き込まれていることに気づかないこともあります。
だからこそ、SNSの利用について、危険性などに関しては、各家庭でもしっかり話し合い、親子で認識することが重要です。
まず、第一に、各家庭での取り組みも重要ですが、ICT機器を学校教育の場でも活用する昨今において、SNSの利用について、学校教育の場でも注意喚起や安全に利用するための啓発活動が大切であると考えます。
インターネットは、企業、医療、福祉、そして教育の現場など、私たちの生活になくてはならないものになりました。
当然のことながら、子どもたちの生活の場にもインターネットは当たり前のようにあり、なくてはならないものになっております。
私たち親は、インターネットはわからない、スマートフォンはわからない、オンラインゲームはわからないと言っている場合ではないかもしれません。
子どもたちたちの安全を守るためにも、これらをしっかり学び、理解しなければならないと思います。
私もオンラインゲームの設定や使い方など、ほとんど知識はありませんでしたが、動画配信などを見て、勉強して、安全に使えるよう学び、対象年齢が高いゲームなどは、子どもと話し合い、やらないようにしております。
正直、それでは得意な分野でないので、苦労しましたが、これらの努力は必要であると考えます。
少し余談となりましたが、
以上を踏まえ、3点伺います。
1. 児童生徒のSNSの利用状況は。
2. 本市の児童生徒がSNSによるトラブルや犯罪にあった事例は。
3. 学校ではSNSの安全利用についてどのような啓発活動を行っているか。
よろしくお願いいたします。
それでは、2点目の質問に移らせていただきます。
本市の交通安全について2点お伺い致します。
まず1点目ですが、交通安全に伴う自治会からの要望で、対応できていないもの状況と今後の対応について伺います。
各務原市交通安全推進協会のホームページを確認しますと、交通事故の件数は年によって増減しておりますが、(減少した年も増加した年もありますが)、掲載されている平成26年からのデータを見ると少しずつ減少しております。
しかし、ここ近年は増加しており、本年の速報値をみると事故の総計が4000件ほどですので、これから慌ただしくなる年末に向け、更なる交通安全への取り組みや呼びかけが大切です。
さて、このような状況下、本市の各自治会から通学路安全をはじめ交通安全に関する要望が数多くされておりますが、本市は、これら様々な要望に迅速に対応していただいております。
また、5年ほど前のことになりますが、大津市で園児たちが巻き込まれた事故をうけ、すぐに本市の各交差点付等を点検し、安全な待機場所となるようガードレールを設置するなど、迅速に対応していただいており、本市の交通安全に対する意識の高さに感謝するところです。
このように交通安全に対して、迅速にまた、高い意識をもって取り組まれている本市でありますが、
要望によっては、市民の安全を守る交通安全にかかわるものであっても、信号の設置や速度制限の変更など市が直接対応できないものもあり、地域の声にお応えできない状況もあるかと思います。
私が住んでいる八木山地域においても、八木山通り(市道1226、1210)鵜沼中学校正門から東側になりますが、の制限速度が50㎞/hを下げて欲しいという要望が、長年でており(年度によっては要望が出ていない年もあると思いますが)、地域の要望が叶っていない状況です。この要望は、颯清会からの要望でも出させていただいております。
この道路では、先月、ご高齢の方がお亡くなりになる交通事故が発生いたしました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
この道路(八木山通り)は、坂祝バイパスへ繋がる道であり、交通量も増え、先ほど述べましたように、制限速度が50kmであるため、東から西向かう場合は下りとなるので、気を付けていても50km以上スピードが出てしまうと地域からご意見をいただいている道路です。先ほど述べました事故と制限速度が直接関わっているものかどうかは、ホームページに掲載されている情報ではわかりませんが、
先ほど述べさせていただいたように、市のみで対応できない要望事項などもありますが、地域事情を把握されている自治会ご要望には、交通事後を未然に防ぐものも数多くあると思いますので、これら要望にお応えするためにも、市から警察、公安への働きかけを引き続き、強くお願いいたします。
以上を踏まえ、交通安全に伴う自治会からの要望で、対応できていないもの状況と今後の対応はどのようになっておりますでしょうか。
次に令和7年4月に開校する「かかみがはら特別支援学校」周辺の交通安全対策についておお伺い致します。
いよいよ来年の4月に「かかみはがら支援学校」が開校します。
私のところにも、地域からの喜びの声や障がいのあるお子さまがいらっしゃるご家庭から期待する声を数多くいただいております。
また、地域では、近くに八木山など自然豊かな里山ふぁあるのでこれらを活用して、かかみがはら支援学校と地域で連携していくことを模索したいという、声もいただいております。
このように期待する声を同時に、開校後は、周囲の環境は大きく変化すると思います。その一つに通勤通学時、下校時の交通状況があり、これらについて、どのような対策を行うのかというお問い合わせの声を地域からります。
今現在も、ら支援学校周辺は、朝は、北側にある鵜沼中学校の生徒や八木山、羽場地区の皆さまが通勤等で、かかみはがら支援学校周辺道路を利用するため、交通量が多い状況です。
このような状況下、かかみはがら支援学校が開校すれば、更に交通量が多くなるなどの課題が発生すると思われます。
この件に関しても令和7年度予算編成に伴う颯清会からの要望事項に載せさせていただきましたが、
以上を踏まえ、開校するかかみはがら支援学校周辺の交通安全対策についてお聞かせください。
以上2点です。よろしくお願いいたします。