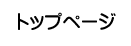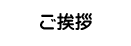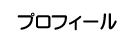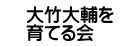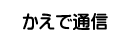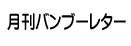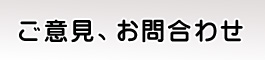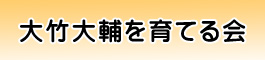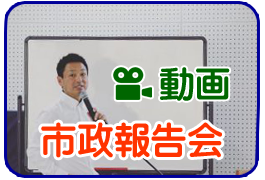令和7年第3回各務原市議会定例会一般質問
【本市の公共交通機関について】
(1)「ふれあいバス」における利用動向と運行コスト高騰の課題に対し、市としてどのような対応策を検討しているのか。
ふれあいバスの利用動向については、鉄道や民間路線バスを補完する地域の移動手段として、日常の買い物や通院、通勤・通学などに利用され、利用者は年々増加しています。
また、人件費や燃料費の上昇により運行コストは高騰しておりますが、これらの必要な経費は、市が財政負担して対応しております。
この負担を任減するには、運行距離や利用者が少ない時間帯の運行本数を減らすことで経費の削減を図るほか、運賃を値上げして収入を増やすといったことも考えられますが、利便性の低下や利用者の負担増をまねくことがないように、できる限り現在のサービス水準を維持していきたいと考えています。
そのために、対応策としては、より多くの方のご利用により運賃収入を増やしていけるよう、みんなで公共交通を支えていく気運を醸成していくことが必要です。
市としましては、今後も安定した公共交通サービスを提供するとともに、日常的な利用促進を図るため、ふれあいバス懇談会等を通じて、市民とともに課題と向き合い、地域の特性やニーズの変化に合わせた公共交通サービスが提供できるよう努めてまいります。
(2)本市における自動運転技術の導入や実証実験について、現時点でどのように検討しているのか。
運転士不足の深刻化により、民間路線バスやコミュニティバスの維持が難しくなっていくことが予想される中、自動運転は運転士不足の解消につながる技術として期待されています。
すでに、運転士ではなく、システムが運転に関するすべての操作を担う「レベル 4」の自動運転に取り組む自治体や事業者もありますが、現段階では、天候や道路状況によっては走行できないこともあるため、市民の交通手段として日常的に利用することが難しい上、導入コストや運行経費も大きな財政負担となります。
また、自動運転はまだ実証段階で完全な無人運転技術が確立されておらず、現状では運転士不足の解決にはなり得ないことから、導入に着手する時期ではないと判断しております。
しかし、将来的には運転士不足を補う有効な手段と考えておりますので、今後も引き続き情報収集に努め、実用化が見込まれる際には、本市における活用の可能性を検討してまいります。
【学校適正規模・適正配置と通学手段について】
(1)学校統合や学区再編を検討する際の基準や手順は、現時点でどの程度明確化しているのか。
まず、学校再編を検討する基準ですが、和2年に策定した「各務原市学校適正規模・適正配置等に関する基本計画」において、「適正化すべき小規模校」を、小中学校ともに6学級かつ児童生徒数120人以下と定めております。
次に、学校再編の手順につきましては、新たに設置した各務原市学校適正規模・適正配置等検討委員会において、今年度から来年度にかけて、学校適正規模・適正配置等の検討を行います。
この検討は、大きく2段階に分かれており、第1段階として和8年春頃をめどに、再編対象校を決定し、第2段階として和8年度中をめどに、具体的な再編案を決定する予定です。
この過程においては、各種説明会や、パブリックコメント等を実施するほか、スマート連絡帳やかわら版等を通じた積極的な情報発信に努めてまいります。
(2)再編により通学距離が延びる地域におけるスクールバス運行の検討状況は。
スクールバスに関しましては、今年、6月から7月に開催した保護者説明会においても、運行を求めるご意見を多くいただいたところです。
今後、学校の再編に伴って、通学距離が延びる地域等におきましては、スクールバスの運行を検討してまいります。
(3)小中一貫教育を行う義務教育学校の導入や、学校施設の防災拠点・地域交流拠点としての活用は、学校の適正規模・適正配置の方向性が定まった後に具体的に検討されるべき課題であると考えるが、本市の見解は。
義務教育学校の導入につきましては、学校の適正規模・適正配置を検討する段階で、その手法の一つとして併せて検討してまいります。
防災拠点や地域交流拠点としての活用につきましては、和7年3月に策定した「各務原市学校建替基本方針」において、その考え方を示したところですが、より具体的なことにつきましては、大竹議員ご発言の通り、学校再編の方向性が定まった後に、検討を深めていく考えです。